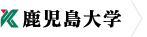専任教員ブログ
博士(後期)課程の大学院生支援に関する新たな制度
伊藤です。
先日、博士(後期)課程に在籍する大学院生に対し、1人当たり年間290万円を支給する取り組みを開始すると文部科学省が明らかにしました。対象となるのは全国に約70,000人いる博士(後期)課程の大学院生のうち、約10分の1に当たる約7,000人とのことです。
博士(後期)課程の大学院生に対する経済的支援の取り組みとしては非常に画期的といえるでしょう。もちろん、日本学術振興会の奨励金獲得以上の狭き門ですので、対象者がこれで十分かと言えば疑問がないわけではありません。それでも、第一歩として非常に重要なものといえると思います。
大学教員を目指す場合の一般的なルートとしては、大学院博士(後期)課程まで進学して博士の学位を取得し、いずれかの大学の公募を突破することになります。以前は、人文系や社会科学系における博士の学位とは、「研究者生活の集大成」と位置づけられるものでした。そのため、私より上の世代では博士の学位を持っていない研究者も少なくありません。これに対して自然科学系では学位取得後に就職というのが以前から一般的であり、人文系・社会科学系でも徐々にそのような流れとなってきています。
しかし、学位を取得すればもれなく職に就けるかといえば、そんなことは全くありません。分野によって相当差があるものの、大学教員のポストは減少の一途です。そのうえ、任期付きのポストも多く、安定した職に就くのは非常に難しくなっています。ただでさえ、学位取得後からのスタートと考えれば既に30代であり、大学卒業直後に就職した同級生が10年以上のキャリアを職場で積んでいます。これに対して、先の見えない大学院生あるいはポスドク生活を送らざるを得ないというのは非常に不安になるのは間違いありません。こうした状況の中では、研究に関心があっても安易に進学を選択することはできなくなりますし、真剣に学生のことを考える教員ほど進学を進めることを躊躇せざるを得なくなります。
当センターで特任助手制度を発足させた背景には、こうした状況に対する課題意識がありました。博士(後期)過程に進学した大学院生が少しでも研究に専念できる状況を提供すること、また、昨今の公募で多く見られるようになった模擬授業に備え、教育能力の向上に努めることなどによって、少しでも博士(後期)課程の大学院生やポスドクの方々の先の見通しを立てられるようにできればと願っています。
毎年、学術振興会の結果が明らかになる時期と年度末になると、特任助手から“卒業”の連絡が来ます。特別研究員に採択されたり、就職が決まったりして、特任助手という立場から旅立っていきます。一抹の寂しさもありますが、気持ちはとても晴れやかであり、今後の活躍を願わずにはいられません。
私は、鹿大への採用決定の報告をした際に、ある先生から言われたことを今でも覚えています。
私が採用されたのは必ずしも私の優秀さを意味するわけではない。
人事には運もタイミングもある。
私よりずっと優秀だけれども運に恵まれず職に就けずにいる人が大勢いることを忘れてはいけない。
常に肝に銘じ、勘違いしないよう自分を戒める言葉だと思っています。
今回の文部科学省による取り組みは、博士(後期)課程で奮闘している人々のごく一部にとってしか救いにはならないのかもしれません。昨今のこうした支援制度は、補助期間終了後は各大学の独自予算で何とかせよというのが定番ですので、採択されたらされたで大学にとっては新たな難題が生じることになるだろうとも予想します。
それでも、学問を、研究を続けていきたいと願う人たちにとっていくばくかでも明るい展望が開ける道が拓かれることを願っています。